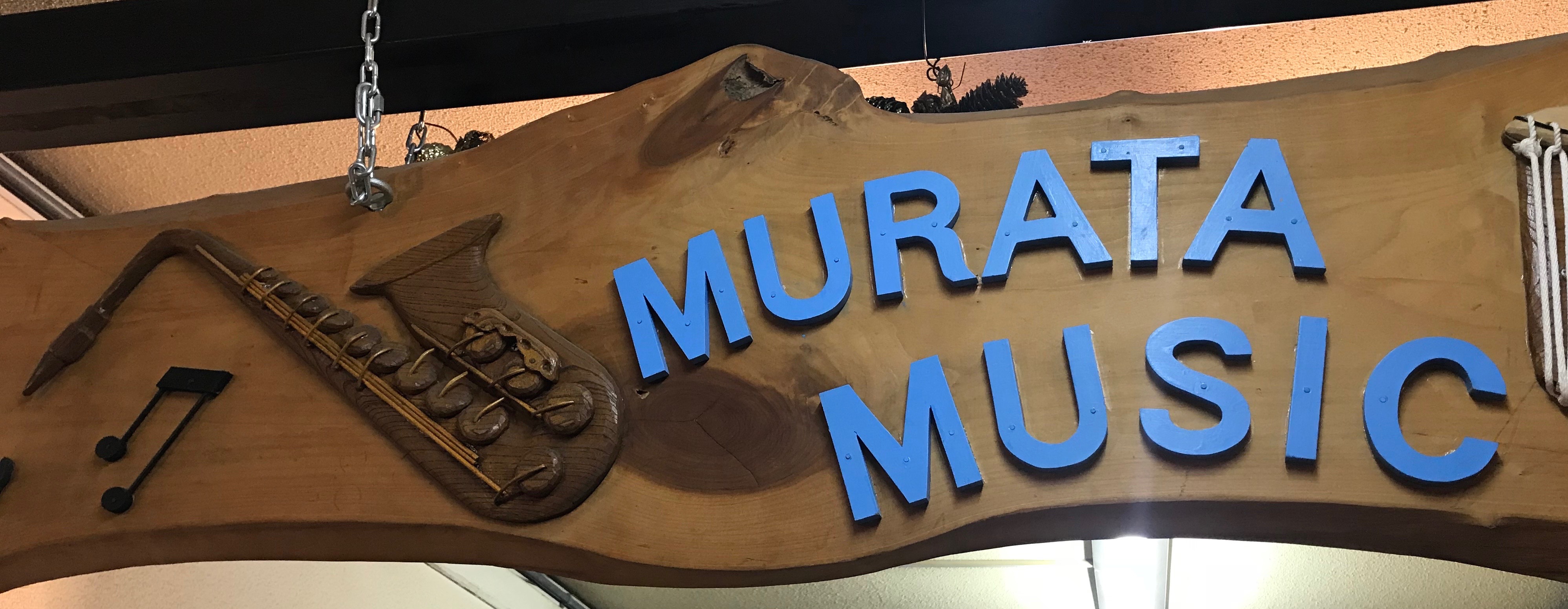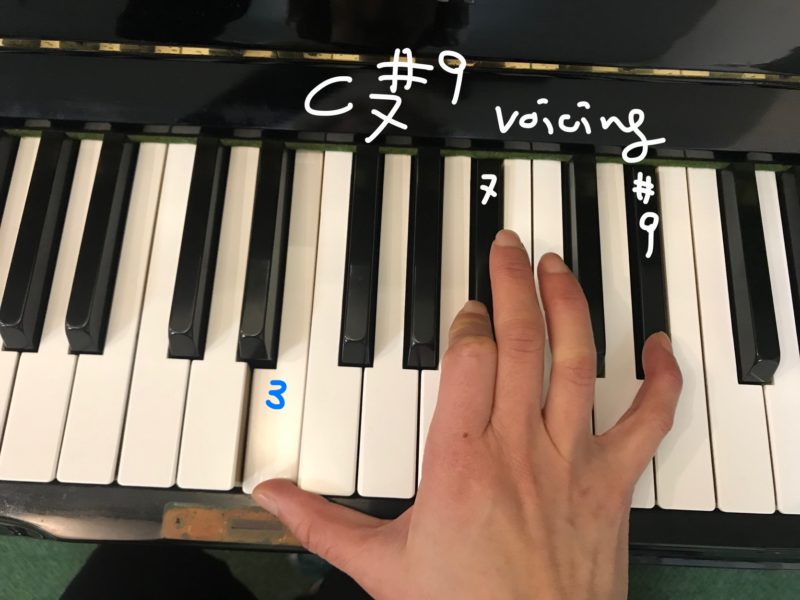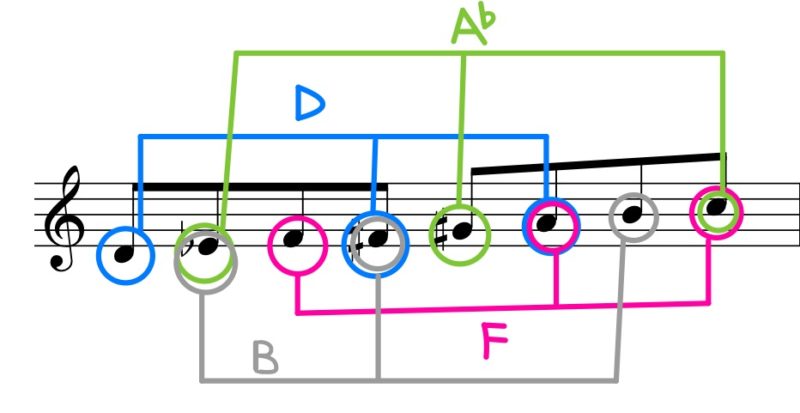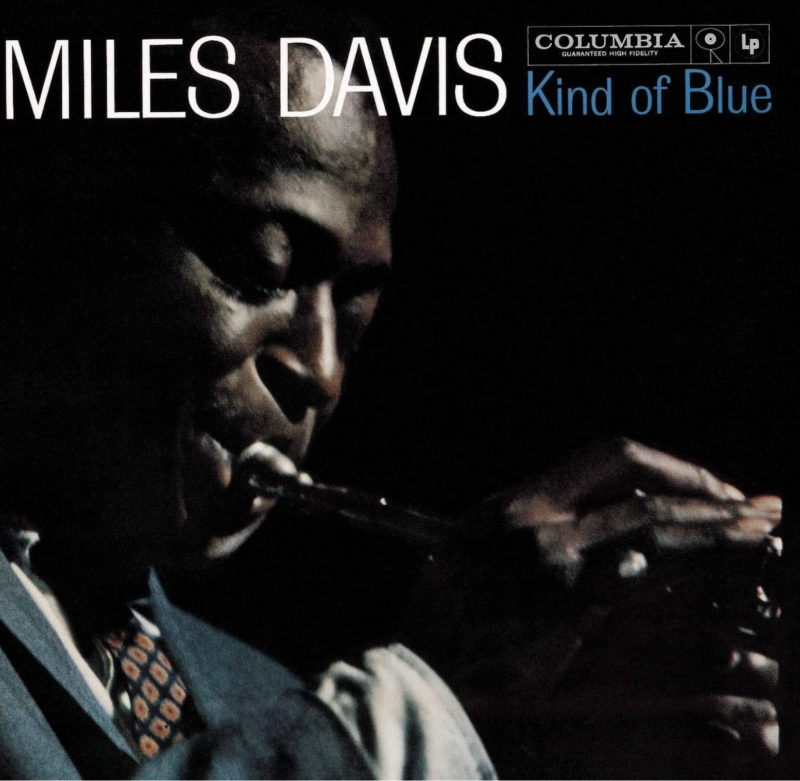出版されている曲集やエチュードの曲順は必ずしも「難易度順」ではありません。
例えば「ジャズ・アルト・サックス実践と理論」「ジャズ・テナー・サックス実践と理論」は2曲目が Confirmation です。独学の方が1曲目から順番に練習した場合2曲目で挫折・・・になりかねません。
また音大受験で使用されている 「48のエチュード」は C dur (Cメジャー、ハ長調)の遅いテンポの曲、早いテンポの曲 a moll (Aマイナー、イ短調)の遅い曲と早い曲、その後は調号が増える順番に曲が並んでおり難易度はバラバラです。
レッスンでは人それぞれに合った難易度で次の曲を指定していますが今回は「ジャズ・サックス実践と理論」の大まかな難易度順とおすすめ音源をご案内します。また楽譜通りの音源はムラータミュージックYouTubeにて順番にアップロードしてまいりますので、練習のお供にして頂けると幸いです。
続きを読む →