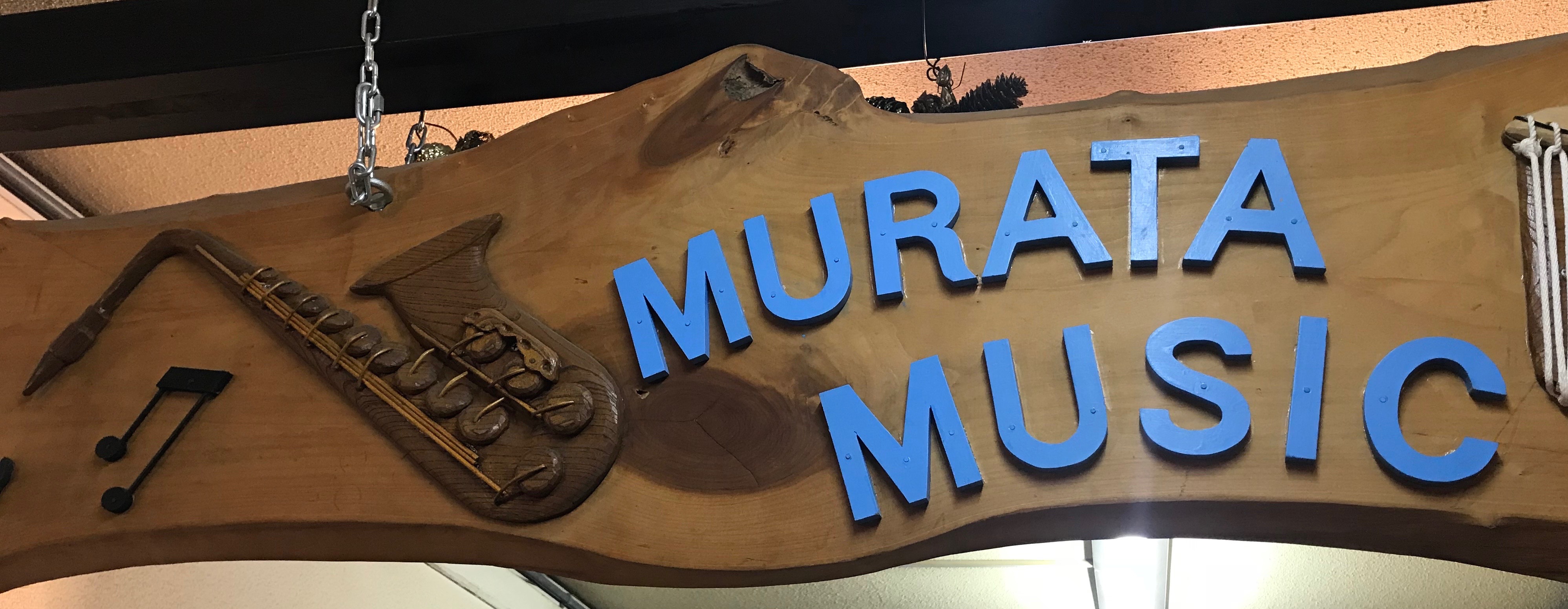前回のブログでは音楽大学入試の試験内容を紹介しました。
今回はその中でも特に「音楽基礎科目」のソルフェージュについて説明したいと思います。
ソルフェージュは「聴音」と「新曲視唱」の2科目があり、学校やジャンル(クラシック、ジャズポピュラー)によって内容が異なります。また、日本の音楽大学と海外の音楽大学も傾向が異なります。
聴音
聴音とは音を聞いて楽譜に書き取る試験です。殆どの学校は教室内の学内放送にて実施されます。内容は学校により少し異なりますが、以下の内容になります。まずクラシック科の内容です。
- 単旋律(8~12小節程度のメロディを書き取ります。)
- 複旋律(2つ同時に流れるメロディーを書き取ります。)
- 四声体和声(和音のソプラノ、アルト、テノール、バスの4つの声部をそれぞれ書き取ります。)
- リズムソルフェージュ(リズムを書き取る学校と口頭で答える学校があります。)
ジャズ科の聴音ですが、国内と海外は少し異なります。 日本の大学の場合クラシックと同じ内容を受験するか、少し難易度が下がったものになる事が多いです。 海外の場合は以下の内容が多いです。
- 単旋律(2小節から4小節程度のジャズのフレーズを書き取ります。)
- 最後の音を書き取る(4小節程度のフレーズを聞き、最後の1音が何かを答えます。)
- インターバル(同時に演奏された二つの音の音程を書き取ります。例:長6度、完全5度など。)
- 曲の調子(何拍子かと言う事と、長調か短調かを聞き分けて答えます。)
- リズムソルフェージュ(実際の楽曲のリズムを答える事が多いです。)
- 自分の楽器でリピートする(試験官が演奏した短いフレーズを楽器で繰り返します。)
では国内の聴音試験の対策について考えてみましょう。
まず単旋律の聴音ですが、調号がシャープ・フラット共に4つくらいまでは聞き取れるようにしておいた方が良いでしょう。さすがにFis dur ( F# major )や B moll ( B flat minor )のような調性は出てきません。 リズムは4拍子、3拍子、8分の6拍子が出てきます。臨時記号も必ず出てくるので同音に挟まれた半音などの聞き取りにも慣れましょう。
複旋律の聴音は調号はシャープ・フラットそれぞれ2つまでが多いようです。長調・短調共に練習しておきましょう。複旋律課題は無い学校も多いので、ご自身の受験校の課題をチェックして下さい。(わからない方はご相談頂ければこちらで調べますよ〜。)
四声体和声が課題の学校は国公立は必ずあります。また私学は科によって無い場合もあります。四声体和声は耳が慣れるまで難しいのでレッスンを受けて慣れて下さい。 聴音に関しては動画も沢山あるので日頃の練習に使う事をお勧めします。
リズムソルフェージュは2種類あり、放送などによって流れる音のリズムを楽譜に書き取るパターンと、初見で与えられたリズム譜を手で叩くパターンがあります。後者の方は左手右手でそれぞれ違うパターンを同時に叩くものもあります。 このリズムソルフェージュに関しては試験に含まれていない学校もあります。受験校によって少しずつ内容が異なるのでホームページ等で資料請求をして確認しましょう。
視唱
視唱は殆どの学校で新曲視唱ですが、コールユーブンゲンと新曲視唱を併用している学校もあります。コールユーブンゲンはあらかじめ範囲が指定されている事もありますので、受験校の課題を調べてみて下さい。
新曲視唱とは12小節から16小節程度のメロディを見て歌う試験です。予見時間は3分程度で歌う前に主和音が与えられます。(加えて最初の歌い出しの音が与えられる学校もあります。) 固定ド、移動ド、どちらでも大丈夫で階名(ドレミ)でも母音唱(言葉なしで歌う)でも構いません。 これも慣れないととても難しいので必ずレッスンを受けましょう。 音感がしっかりしていても歌うことに慣れていないと音程がぶれやすいのと、思わぬ臨時記号や転調(学校により傾向があります。)があるので、慣れる事が必要です。 ただし、慣れると必ず出来るようになります。
以上が音楽基礎科目の内容となります。「嫌だなぁ。」と思う方も多いかも知れませんが、これらが出来るようになると実技演奏にも良い影響があります。またミュージシャンとして活動して行く上で非常に大切なスキルとなりますので、これを期にソルフェージュを得意科目にしてみてはいかがでしょうか。
また、受験生でなくてもイヤートレーニングは楽器演奏者には良い影響があります。わざわざレッスンとまでは行かなくても動画で「ear training」を検索してみると結構面白い動画もありますよ。 大人になってからでも(何歳からでも)必ず音感は身につきますので、遊び半分でチャレンジしてみて下さいね!